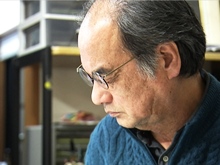広島市内から高速道路で約1時間の農村地帯にある北広島町。この町が今、ある伝統芸能で沸き立っています。その伝統芸能は「神楽」。
本来、神楽は農業の実りに感謝して年に一度、秋に神社で神職が奉納する農耕儀礼のひとつでしたが、この神楽を「農村の娯楽」として発展させ定着していました。特に物語の舞台になる北広島町は、人口約2万人の小さな町に60を超える神楽団があり、「神楽の聖地」とも呼ばれるほどです。
しかしこの北広島町でも、例外なく過疎化が進み、農村の娯楽として長年親しまれてきた伝統芸能に影を落とし始めます。1990年代に入ると急速に進む過疎化と高齢化、農業の衰退に伴い、神楽団を維持するのもままならない状況に陥りました。
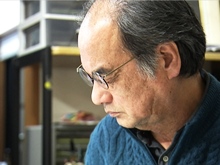
「このままでは神楽がなくなってしまう」と危機感を募らせた人たちが動き出します。神楽を魅力ある芸術に仕立てることで農村に新しい産業が生まれると確信する人たちです。当初は伝統芸能のスタイルを崩すものと周囲の猛反発を招きましたが、それまでの常識を覆す派手な衣装や照明、面や衣装の早変わり、舞台装置を駆使して「魅せる神楽」に生まれ変わらせ、神楽は舞台芸術として飛躍しました。それがいつしか「スーパー神楽」と呼ばれるようになり町にブームを巻き起こします。

スーパー神楽は例えば大蛇のセットを毎回壊しますが、その度に新しいセットが必要になり、激しい動きで鬼の面などの寿命も短いため、そこに職人の仕事が生まれ、北広島町には面作りや小道具作りを生業とする職人も出始めます。今では、神楽を中心とした産業が成り立っているほどです。
さらに過疎化が進む北広島町ですが、20歳代から40歳代が多い神楽団員は、神楽があるから町を出ていかないという人や、神楽団に入りたいとわざわざ都会から移住して来る若者が増えつつあります。神楽団員は、今では、過疎と高齢化に悩む農村にあって「希望の光」にもなっているのです。

また、スーパー神楽人気で従来の神楽にも関心が高まり、町内で公演される神楽には都市部から多くの人が押し寄せることになります。そして、海を越えて海外にも広がりを見せ始め、町外では週1回、定期的に広島市中心部のホールで定期公演が開催されており、日本の伝統文化に興味のある外国人の姿が増えて来ます。2000年以降は、ロシア、中国、メキシコ、ブラジルでの海外公演も行いました。
町に活気をもたらした「スーパー神楽」とそれに関わる人たちの奮闘をご覧ください。
編集後記
ディレクター:大知 徹也(RCCフロンティア)
神楽の演目に「紅葉狩」というものがあります。人里離れた山で紅葉狩りの酒宴を楽しんでいる美女たちが実は鬼だった、という大まかなストーリーなのですが、今回取材で伺った神楽大会の演目が4団体全て「紅葉狩」だったことがあります。実はそれが成立するくらい同じ演目でも神楽団によって中身が違うのです。神楽団ごとに物語の解釈も違えば登場人物も違う。お客さんはそれぞれの違いを楽しむのです。今度ゆっくりと鑑賞したいと思わせる企画でした。
広島市内でも毎週定期公演を夜に行っています。もし広島を訪れる機会がございましたら、昼間観光した後に神楽鑑賞を楽しんでみるのはいかがでしょうか。